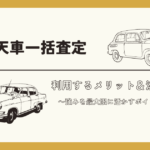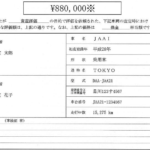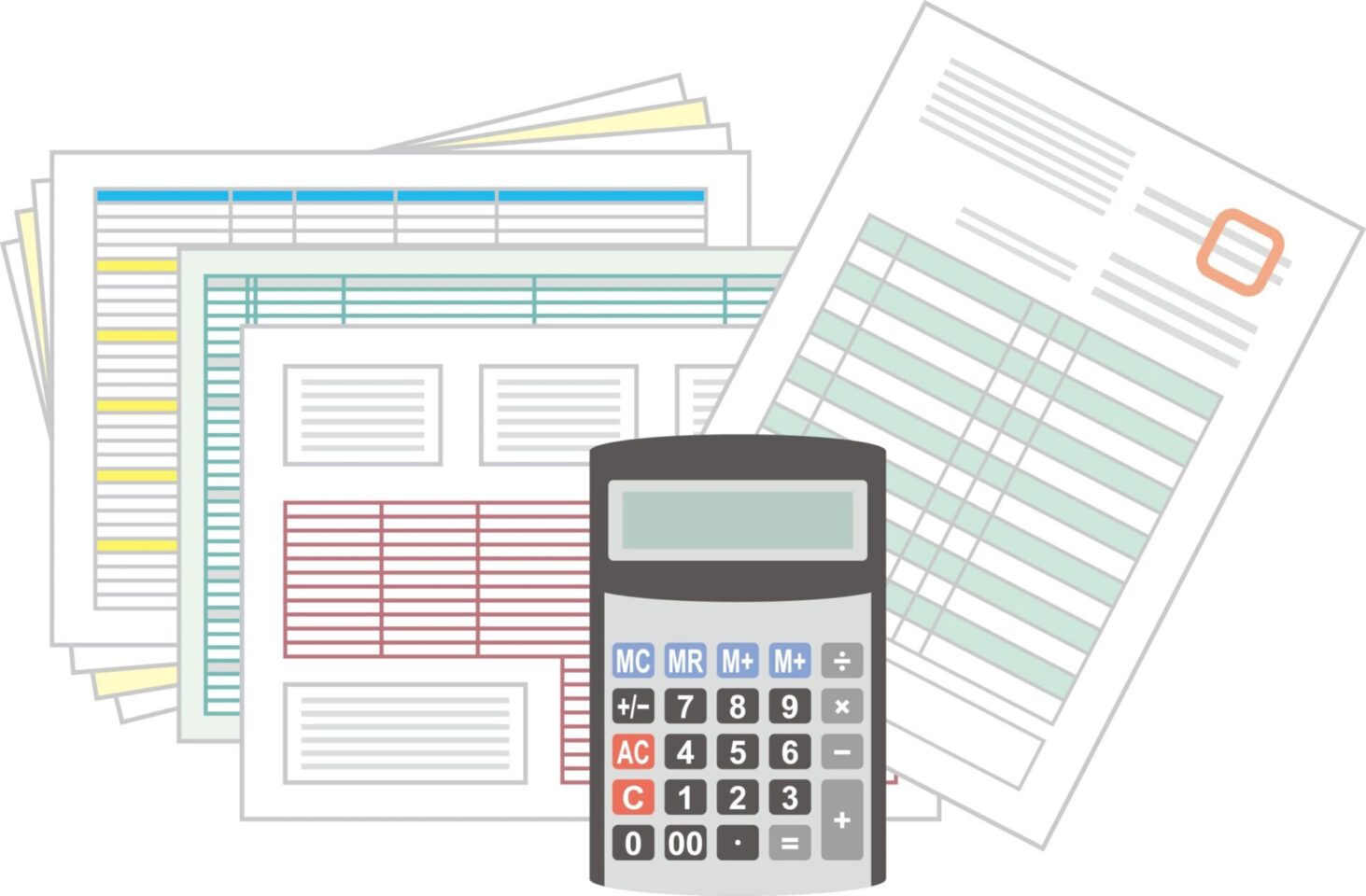
営業などの事業活動で使っていた車を売却した場合、その仕訳ってすごく分かりにくいですよね。
しかも、法人と個人事業主で計上方法が異なるのを知っていましたか?
具体的には、法人と個人事業主にはそれぞれ4つの仕訳方法が用意されているのです。
この違いを把握しておけば、事業内容に合った仕訳方法が選択できます。
そこで今回は、法人と個人事業主の仕訳方法について解説します。
リサイクル預託金や減価償却費の処理方法についてもお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
会計における車の考え方
車売却の際の仕訳を理解するには、まず購入から現在まで、どのように車が計上されているのか知る必要があります。
そもそも、車は「経費」ではなく「資産」です!
購入したときには以下のように計上します。
- 車両:車両運搬具(資産) *減価償却対象
- リサイクル預託金:預託金(資産) *減価償却対象外
車両の資産価値は、減価償却分を損金計上しているため、減価償却分だけ毎年減少します。
また、車両を売却したときは「車両売却額-現在の車の資産価値=利益」です。
以上が、会計における車の基本的な考え方になります。
減価償却費の計算方法
続いては、減価償却費の計算方法について解説します。
まず、新車で購入場合は法定耐用年数を基に計算します。法定耐用年数は普通乗用車なら6年、軽自動車なら4年です。
車両購入費を法定耐用年数で割った金額が、1年間の減価償却費となります。
また、あなたの車が中古車なら自分で耐用年数を計算しなければなりません。
法定耐用年数を終えていない中古車の具体的な計算式は以下の通りです。
- 耐用年数=(新品の耐用年数-中古資産の経過期間)+(中古資産の経過期間×20%)
例えば、初度登録から2年9か月経過した普通乗用車を購入したなら、まずは経過年数を月単位に直します。
2年9か月を月単位にすると33か月。
この33か月を上記の計算式にあてはめます。
- 45.6か月=(新品の耐用年数6年×12か月-中古資産の経過期間33ヶ月)+(中古資産の経過期間33ヶ月×20%)
45.6か月を年単位に直すと3年9.6か月です。
そして、中古資産の耐用年数に小数点以下が発生している場合、1年未満の小数点以下は切り捨てとなります。
つまり、3年9.6か月は3年です。
計算結果の耐用年数は2年より大きいので、中古資産の耐用年数は3年となります。
以上の計算式を使って耐用年数が2年未満と算出されたら、耐用年数は2年です。
法人と個人事業主にはそれぞれ4つの仕訳方法がある
車の売却金額の仕訳方法は、法人が4つと個人事業主が4つの合計8つあります。
具体的には以下の組み合わせによってできる8つです。
- 法人 or 個人事業主
- 減価償却:直接法 or 間接法
- 消費税の処理:税込 or 税抜
次の項目では、法人・個人事業主それぞれ4つの方法で仕訳方法を解説します。
その際の前提条件は以下を使っていきます。
【条件例 ・車は3年乗って売却】
✔ 216万円(税込・リサイクル預託金を除く)の普通乗用車を購入
✔ 売却額は86万4000円(税込・リサイクル預託金含む)
✔ 3年間の減価償却累計額は108万円(税込)
✔ 期首の車の帳簿価額は108万円(税込)
✔ リサイクル預託金は1万8000円
✔ 消費税は8%
法人の4つの仕訳方法
まずは、法人の4つの仕訳方法を解説します。
1.法人・直接法・税込
車のような固定資産を購入した場合、1度に全額を損金として経費計上できません。
耐用年数に応じて減価償却する必要があります。
直接法とは、あらかじめ減価償却費から固定資産を差し引いて記入する方法です。
最初は、車の売却額86万4,000円を「現預金」の借方に記入。
貸方には、車の購入費用216万円から減価償却累計額108万円を差し引きます。
そして、車の帳簿価額108万円を「車両運搬具」として借方に記入してください。
また、車購入時のリサイクル預託金1万8,000円も借方に記入しましょう。
加えて、売却による損失額が23万4,000円なので、その金額を「車両売却損 or 固定資産売却損」として借方に記入すればOKです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 現預金 | 864,000円 | 車両運搬具 | 1,080,000円 |
| 車両売却損 | 234,000円 | 預託金 | 18,000円 |
| 合計 | 1,098,000円 | 合計 | 1,098,000円 |
2.法人・直接法・税抜
税抜であっても基本的に課税される金額は同じです。
異なるのは売却額の消費税を「仮受消費税」として、別で記入するという点になります。
当然、車両運搬具も税抜にしなければなりません。
消費税分を差し引くため、車両売却損と車両運搬具の金額は減ります。
ちなみに税込では、「租税公課」という項目が追加されるので実際の損益は同じです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 現預金 | 864,000円 | 車両運搬具 | 1,000,000円 |
| 車両売却損 | 218,000円 | 仮受消費税 | 64,000円 |
| 預託金 | 18,000円 | ||
| 合計 | 1,082,000円 | 合計 | 1,082,000円 |
3.法人・間接法・税込
間接法とは、減価償却累計額を固定資産から差し引かず貸方に仕訳する方法です。
そのため、減価償却累計額は借方に記入します。
あとの記入方法は直接法・税込と同じです。
ちなみに、車の売却は課税取引に該当します。そのため、売却額86万4,000円に対しての課税。
リサイクル預託金に関しては非課税売上に分類されるのです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 現預金 | 864,000円 | 車両運搬具 | 2,160,000円 |
| 減価償却累計額 | 1,080,000円 | 預託金 | 18,000円 |
| 車両売却損 | 234,000円 | ||
| 合計 | 2,178,000円 | 合計 | 2,178,000円 |
4.法人・間接法・税抜
法人・間接法・税抜の場合、減価償却累計額と仮受消費税の2つを記載します。
そのため項目の数は1番多いのが特徴です。
車両売却損については、法人・直接法・税抜と同じになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 現預金 | 864,000円 | 車両運搬具 | 2,000,000円 |
| 減価償却累計額 | 1,000,000円 | 仮受消費税 | 64,000円 |
| 車両売却損 | 218,000円 | 預託金 | 18,000円 |
| 合計 | 2,082,000円 | 合計 | 2,082,000円 |
個人事業主の4つの仕訳方法
続いては、個人事業主の4つの仕訳方法を解説します。
1.個人事業主・直接法・税込
個人事業主は、法人と異なり車を売っても「売却」ではなく「譲渡」扱いとなります。
そのため、個人⇒法人への資産譲渡という「譲渡所得」になるのです。
法人では、「車両売却損」としていた処理項目は「事業主貸」に変更して記入します。
ただし、「車両売却損」⇒「事業主貸」に変わるだけで金額は変わりありません。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 現預金 | 864,000円 | 車両運搬具 | 1,080,000円 |
| 事業主貸 | 234,000円 | 預託金 | 18,000円 |
| 合計 | 1,098,000円 | 合計 | 1,098,000円 |
2.個人事業主・直接法・税抜
税抜の場合は「事業主貸」の金額が税込よりも減ります。これは、法人のときと同じですね。
また、最終的には「租税公課」で調整されるため課税対象額は同じです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 現預金 | 864,000円 | 車両運搬具 | 1,000,000円 |
| 事業主貸 | 218,000円 | 仮受消費税 | 64,000円 |
| 預託金 | 18,000円 | ||
| 合計 | 1,082,000円 | 合計 | 1,082,000円 |
3.個人事業主・間接法・税込
この仕訳方法では、減価償却累計額を省略市内でいち項目として記入。
法人では「車両売却損」だった項目を「事業主貸」として記載していきます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 現預金 | 864,000円 | 車両運搬具 | 2,160,000円 |
| 減価償却累計額 | 1,080,000円 | 預託金 | 18,000円 |
| 事業主貸 | 234,000円 | ||
| 合計 | 2,178,000円 | 合計 | 2,178,000円 |
4.個人事業主・間接法・税抜
この仕訳方法では、減価償却累計額と仮受消費税の2つを項目として記載。
加えて、「車両売却損」を「事業主貸」として計算します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 現預金 | 864,000円 | 車両運搬具 | 2,000,000円 |
| 減価償却累計額 | 1,000,000円 | 仮受消費税 | 64,000円 |
| 事業主貸 | 218,000円 | 預託金 | 18,000円 |
| 合計 | 2,082,000円 | 合計 | 2,082,000円 |
直接法と間接法の違い
直接法と間接法の違いは、車の資産価値から減価償却費を差し引いて記入するかどうかです。
直接法では、売却時の車の価値から減価償却費を引いた金額を記入します。
それに対して間接法では、購入時の価格に減価償却費をプラスして記入し、帳簿上で減価償却を計算するのです。
直接法で記入すれば、貸借対照表における資産の科目と一致するため、一時の資産状況の一覧には適しています。
間接法は手間がかかる一方で、購入時の価格が確認できるメリットがあるのです。
税込と税抜の違い
税込と税抜は、どちらでなければダメという決まりはありません。
税込で記入すれば簡単ではある一方で、税抜金額が一覧できないという欠点があるのです。
消費税の課税事業者であれば、消費税を加えた仕訳の方が向いているでしょう。
消費税の還付を受ける場合があるなら、税抜を選択したほうが見やすいので便利です。
リサイクル預託金の仕訳には注意が必要
そもそもリサイクル預託金とは、廃車時にエアコンのフロン類やエアバッグ、シュレッダーダストの処理をするための資金です。
新車購入時に支払うお金なので、本来は廃車時にかかるお金を預けているだけ。
そのため、有価証券とみなされて、支出ではなく資産として判断されるのです。
有価証券として保持している状態では、リサイクル預託金に消費税は課せられません。
中古車として売却する際も、「有価証券を譲渡した」と判断されるため非課税になるのです。
その一方で、リサイクル預託金の支払い時に同時に払う「資金管理料」は支出とみなされます。
つまり、消費税がかかるわけです。
しかし、これを理解していないと、「同時に支払っているのだからリサイクル預託金も支出だろう」と勘違いする恐れがあります。
廃車時には、リサイクル預託金を用いて廃車処理し、その際に消費税の課税対象として扱われるのです。
リサイクル預託金の消費税の支払い義務は、最後に車を手放した人だと理解する必要があります。
期中に売却した場合の減価償却費の計上方法
期中に車を売却した際に気になるのが「期首から売却時までの減価償却費は計上する必要あるの?」という点ではないでしょうか。
結論を言ってしまうと、実務業はどちらでも構いません!
ただし、法人税法上は以下のように記載されています。
第三十一条
内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
引用元:総務省行政管理局e-Gov「法人税法」
簡単に言ってしまうと、「各事業年度終了の時において有する減価償却資産」なら減価償却費として計上できるというわけです。
加えて法人税の確定申告書別表16は、事業年度末に存在する資産しか記載されないため、期中の減価償却費は計上しない方が良いと言えるでしょう。
とはいっても、売却時までの減価償却費を計上してもしなくても、最終的な損益には影響がないのが実情です。
同様に個人事業主の場合も、「その年の12月31日臭いて有する減価償却資産」について減価償却費を計上できるとされています。
第四十九条
居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする
引用元:総務省行政管理局e-Gov「所得税法」
ただし、個人事業主の場合は所得税。法人税と異なり国税庁から「売却時までの減価償却費を計上して所得計算をしても差し支えない」との通達は出ています。
所得税になると、車の譲渡(売却)による売上は譲渡所得として計算します。
以下のどちらを選ぶかによって所得が異なるわけです。
- 売却時までの減価償却費を事業上の減価償却費にするか?
- 譲渡所得の計算時に取得費を含めるか?
このように、法人税ならどちらを選択しても所得に影響はありません。
しかし、所得税になると影響が出るので、国税庁は個人事業主に対して通達をしているのです。
個人事業主の方で、どちらが良いのか分からない場合は、税務署や税理士に相談するようにしてください。
まとめ
今回は、車売却の仕訳について解説しました。
法人と個人事業主それぞれに4つの仕訳方法があり、少し複雑に感じたのではありませんか?
しかし、ポイントさえ押さえて取り組めば、無理なくできるようになります。
また、どうしても自分では難しいと感じたなら、税理士のような専門家に教えてもらうという方法もあるので、その方法も検討してみてください。